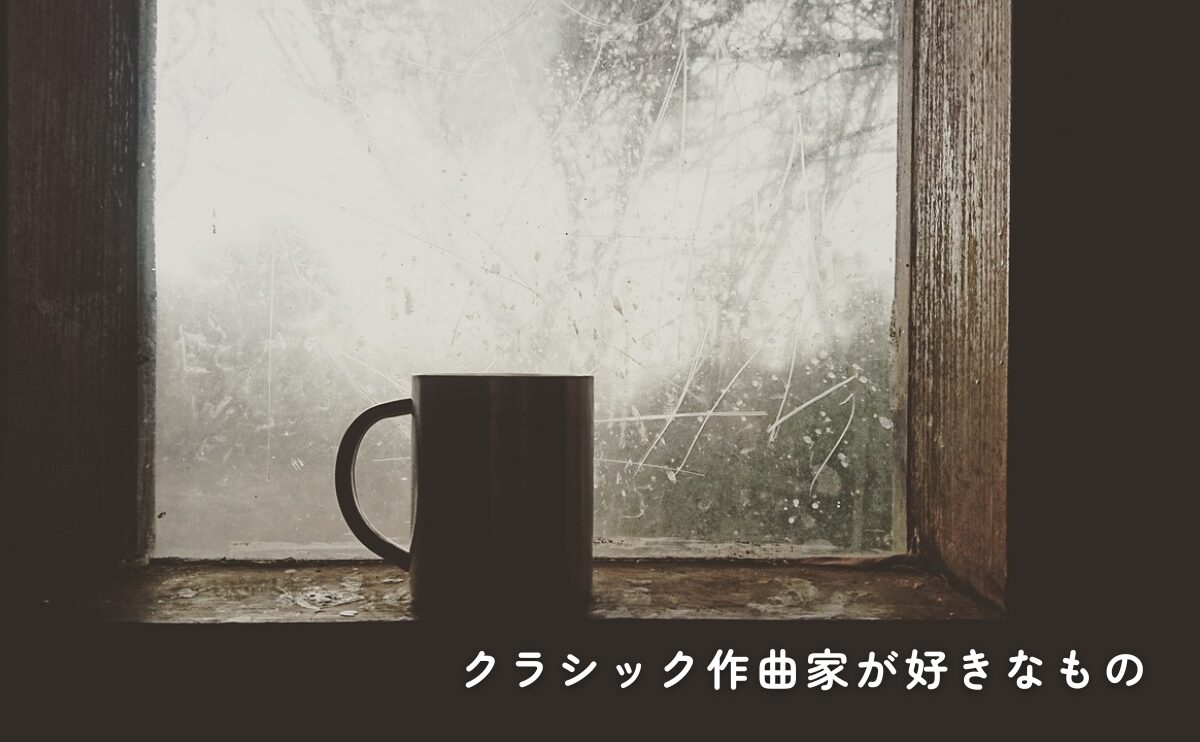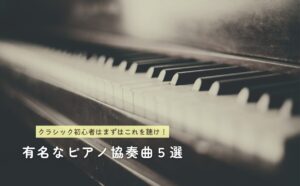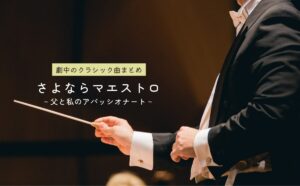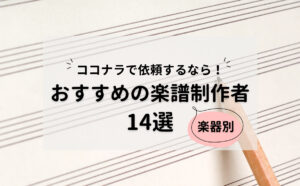偉大なクラシックの作曲家といえども、それぞれ好きな食べ物や習慣があります。
音楽だけ聴いていると、私たちとは次元の違う世界にいるかのようにさえ感じられますが、彼らの日常生活をのぞいてみると、同じ人間なんだなぁと親近感がわくことも。
この記事では、クラシックの作曲家が好きだったもの~3つのエピソードをお届けします。
ショパンが愛したチョコレート

ショパンとチョコレートにまつわるエピソードは、彼のパートナーであった作家ジョルジュ・サンドとの関係に関連しています。
ショパンは非常に繊細な性格で、健康もあまり良くなかったため、サンドは彼の健康管理に細心の注意を払っていました。
サンドはショパンの健康のために、彼に特別な飲み物を用意していました。それが、ホットチョコレートでした。
ホットチョコレートとは、チョコレートとミルクで作る、温かい飲み物。フランス語でショコラ・ショーともいいます。
サンドは、ショパンが消化に問題を抱えていることを知っており、彼の体に負担をかけないように、栄養価が高く消化しやすいホットチョコレートを作ってあげていたようです。
ホットチョコレートは、当時のフランスでは非常に人気のある飲み物で、特に上流階級や芸術家の間で愛飲されていました。
ショパンもこのホットチョコレートが大好きで、毎朝、サンドが作ったホットチョコレートを飲むのが習慣となっていました。
甘党であったショパンは、さらにスミレの砂糖漬けを入れて飲むのが好きだったとか。
このエピソードは、ショパンの繊細な体質と、それに対するサンドの献身的なケアを象徴するものとしてよく引用されます。また、ショパンがいかに繊細であったか、そしてサンドが彼をどれほど大切にしていたかを示す一例でもあります。
下の本では、ショパンのエピソードと共に現地のたくさんの写真が載せられていて、ショパンが毎朝のように飲んでいた、ホットチョコレートを作っていた鍋の写真も載っていました。(今も残されているジョルジュ・サンドの館に現存しているようです。)
鉄道オタクなドヴォルザーク

ドヴォルザークの鉄道オタクなエピソードは有名です。
ドヴォルザークが生きた19世紀は鉄道が急速に発展していった時代で、彼が4歳のころには、家のすぐ近くにも鉄道が敷かれるようになりました。そのことがドヴォルザークを鉄オタへの道へと突き動かしたのかもしれません。
毎日のように列車を見に行くのは当然のことで、駅の時刻表や、車体番号、運転士の名前まで暗記したり、音で異常を察知して駅員に知らせ、事故を未然に防いだり。鉄ヲタをかじっている程度のモノではありません。
43歳のころに作曲した交響曲第7番の第1楽章には、プラハ駅に到着する列車のリズムや音が反映されていると言われています。
50歳でニューヨーク・ナショナル音楽院院長となる依頼を受けてアメリカへ渡ってからも、鉄道への熱意は変わりません。
毎日出勤前に、音楽院とは反対方向にある駅にわざわざ寄って車体番号をチェックし、出勤していたそうです。
アメリカで作曲した交響曲第9番『新世界より』(新世界=アメリカ)の第4楽章の冒頭はまさに、機関車がゆっくりと走り出し、徐々にスピードを上げていくようだ、と言われています。(ドヴォルザークが「鉄道を音楽にした」とはっきり言っているわけではない)
現代では、ヨーロッパの国際特急列車に「アントニン・ドヴォルザーク」号という、ドヴォルザークの名前を冠した列車が運行されています。(チェコとオーストリアにちなんだ名前が付けられた列車がいくつかあり、そのうちのひとつ)
もしも、ドヴォルザークが生きていた時代にそんなことがあったら…
作曲活動は引退して、毎日この列車に乗って過ごしていたかもしれませんね。
バッハとコーヒーカンタータ

コーヒーが好きなクラシック音楽家といえば、毎朝60粒数えてコーヒーを飲んでいたベートーヴェンが有名ですが、バッハも大のコーヒー好きでした。
一日に何十杯も飲むほどで、遺品の中には高級なコーヒーポットやカップが含まれていたとのことです。
バッハは(今でいうサラリーマンのような)雇われの宮廷音楽家だったので、非常に多忙な生活を送っていましたが、その合間をぬって、当時流行っていたコーヒーハウスにもよく出かけていました。
当時のコーヒーハウスとは、今でいう喫茶店やカフェのような落ち着いてコーヒーを楽しむ場、というよりは、学者や詩人、作家などが集まり意見を交わすなどの社交場として大人気でした。
そのうちコーヒーハウスでは音楽も興じられるようになり、バッハも楽団を引き連れて「ツィマーマンのコーヒーハウス」と呼ばれる当時の有名なカフェで演奏活動を行いました。
そして、そこで披露するために作曲したのが『コーヒーカンタータ』。当時社会問題となっていた「カフェイン中毒」を題材とした音楽を作ったのです。
カフェイン中毒の娘と、なんとしてもコーヒーをやめさせようとする父親とのやり取りを、面白おかしく描いています。
だいぶかいつまんでいますが、以下のような歌詞です。(歌詞を書いたのはバッハではありません。)
娘
「コーヒーってなんて美味しいのかしら。日に3度のコーヒーが飲めなければつらすぎて痩せちゃうし、千のキッスよりも大好き!」
父親
「なんて娘だ。コーヒーをやめなければ、スカートも、帽子の飾りも買ってやらん。」
娘
「そう、全然OK!」
父親
「散歩に行くのも、窓から外を眺めるのもダメだ。」
娘
「コーヒーさえあれば大丈夫!」
父親
「けしからん。では結婚もダメだ!」
娘
「えぇ!それは困る!じゃあコーヒーやめるわ。」
父親
「そうか、良かった。では結婚相手を探しに行こう。」
娘
「結婚する相手は、『いつでもコーヒー飲んでいいよ』という人じゃなきゃだめよ。」
コーヒーの香りが立ち込める店内で、美味しいコーヒーを飲みながら、コーヒーカンタータを聴いた人々の顔が目に浮かぶようですね。
まとめ
チョコレートや鉄道、それにコーヒー。
どれも私たちの身近にあるものばかりですね。
次にそれを飲んだり見たりしたときは、ぜひ今日の3人の作曲家のことも思い出してみてください。