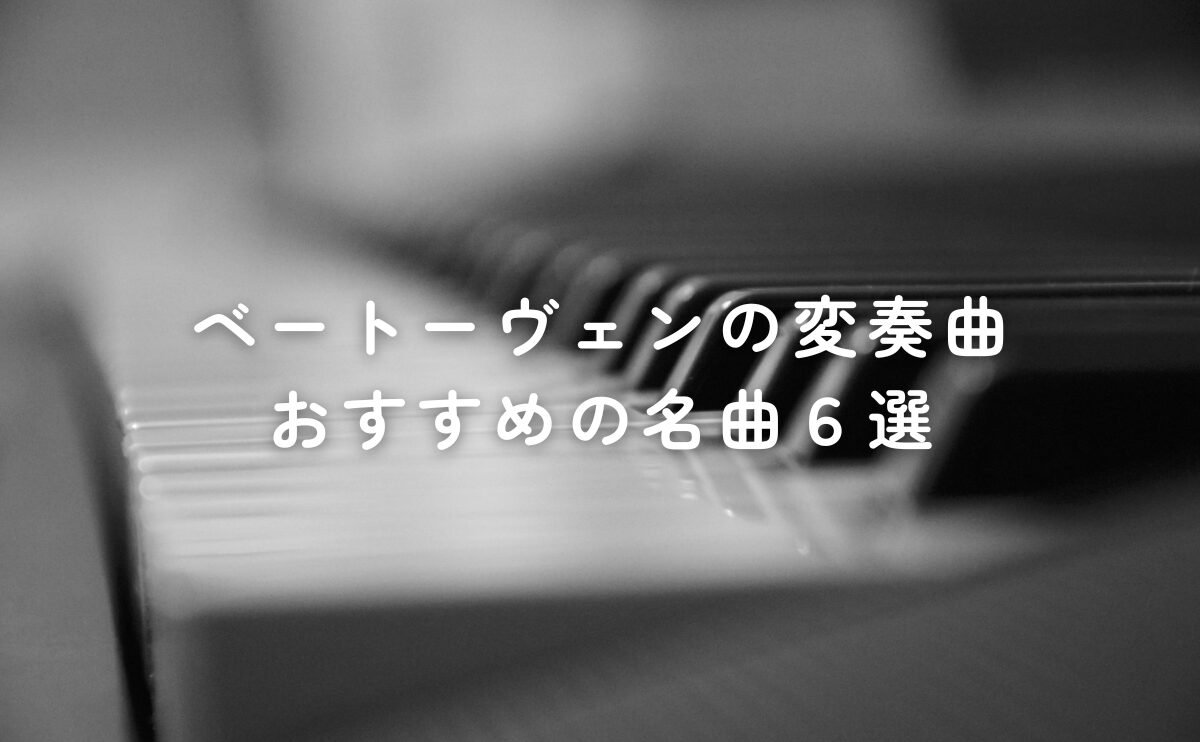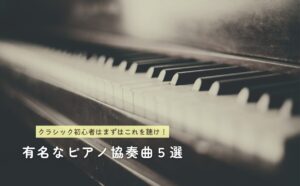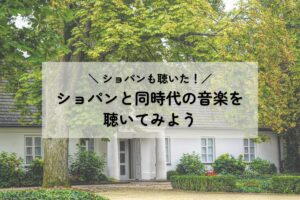ベートーヴェンといえば、《運命》や《月光》など、有名な交響曲やピアノソナタを思い浮かべる人が多いかもしれませんね。
でも実は、ベートーヴェンは即興演奏で名を挙げた「変奏曲の名手」でもありました。
この記事では、ベートーヴェンの変奏曲に関するエピソードと、おすすめの変奏曲を5つご紹介したいと思います。
はじめに:ベートーヴェンと変奏曲
変奏曲と即興演奏のつながり
変奏曲とは、同じ主題(メロディ)をもとに、色々な形に変えて演奏する音楽です。
一方、即興演奏とは、その場で自由にメロディを作り演奏する音楽ですが、ただただ思いついた音楽をやみくもに演奏しているのではなく、大抵の場合はテーマとなる主題(メロディ)をどんどん展開させていきます。
これは即興演奏が基本のジャズも同じです。
変奏曲との違いは、それを楽譜に書き起こすことはしないということです。
変奏曲は、即興的な発想を元にしながらも、緻密な構成で書かれた作品です。
つまり、変奏曲は即興演奏の延長線上にあるともいえるのです。
即興演奏で名を上げた若きベートーヴェン
ベートーヴェンは小さな田舎町ボンで生まれましたが、音楽家として成功するために音楽の都ウィーンへとやってきました。
しかし、当時のウィーンにはすでに有名な作曲家やピアニストがたくさんいて、簡単に名前を売るのは難しい状況。
そんな中、ベートーヴェンが一躍有名になったのが「即興演奏のピアノ対決」です。
ウィーンでは、「どちらがすごいピアニストか」を決めるために、その場でテーマを与えられ、即興でピアノを演奏する対決がよく行われていました。
ベートーヴェンはこの即興対決で次々と勝ち、「即興の天才」と呼ばれるようになったのです。
特に有名なピアノバトルとして挙げられるのが、当時ウィーンの三大ピアニストとして知られていたヨーゼフ・ゲリネクとの対決。
ゲリネクは、モーツァルトにも認められていた変奏曲の名手です。
田舎者の若造を相手に意気込んで試合にのぞんだゲリネクですが、ピアノバトルを終えた翌日にはすっかり意気消沈し、このように語っていたとのことです。
『あの若者は人間じゃあない、悪魔ですよ。……とにかく彼はクラヴィーア[の即興演奏]で、われわれがこれまで思ってもみなかった至難の業と効果を発揮したんです』
引用元:ベートーヴェンの生涯(青木やよひ 著)
「だれもが聴いたことがあるテーマ」の変奏曲
『見よ勇者は帰る』の主題による12の変奏曲 ト長調 WoO 45
まずは実際に曲を聴いてみてください。
表彰式の音楽として聴きなじみのあるこの音楽、実はクラシックなのです。
元の曲はヘンデルが作曲した『見よ勇者は帰る』というオラトリオのコーラス部分。
これをベートーヴェンが、演奏旅行に出向いた土地の国王のために、ピアノとチェロの変奏曲として作曲しています。(自分でもチェロを演奏する音楽好きな国王だった)
ベートーヴェンはその国王の前で、宮廷首席チェリストのジャン=ルイ・デュポールとともに、同じ時期に作曲したチェロソナタの演奏も行っています。
ちなみに、このジャン=ルイ・デュポールが持っていたストラディバリウス『デュポール』は今も現存していて、最近ではロストロポーヴィチ(上に貼った音源のチェリスト)が所有していたそうです。(この録音で使用していたかは不明)
クラシック好きなら聴いたことがあるかも?な変奏曲
エロイカ変奏曲 変ホ長調 Op.35
この曲を聴いて、「あれ?どこかで聴いたことがある…」 と思ったクラシックファンも多いはず。
それもそのはず、ベートーヴェンの交響曲第3番《英雄(エロイカ)》の第4楽章で使われている主題(=メロディ)が、ここでも登場しているのです。
実はこの主題、ベートーヴェンの4つの異なる作品に使われています。これほど同じ主題が繰り返し使われるのは、とても珍しいことです。
同じ主題が使われている作品↓
- 「12のコントルダンス」WoO14 第7曲(1791-1802年)
- バレエ音楽「プロメテウスの創造物」Op.43 第16番(1800-1801年)
- エロイカ変奏曲 Op.35(1802年)
- 交響曲第3番「英雄」Op.55 第4楽章(1802-1804年)
作曲年を見ると分かるように、エロイカ変奏曲の方が、交響曲「英雄(エロイカ)」よりも先に作曲されています。
実は、当初は「ピアノのための変奏曲」という名前しか付けられていなかったこの作品。
しかし、後から作られた交響曲があまりにも有名になったため、「エロイカ」の名前が、先に作られた変奏曲にも使われるようになった、というわけです。
『娘か女か』の主題による12の変奏曲 ヘ長調 Op.66
こちらはモーツァルトのオペラ『魔笛』の「娘か女か」を元にした変奏曲です。
まずは原曲をどうぞ。
「かわいい奥さんが欲しいなぁ」と歌っています。
そして、↓のがベートーヴェンの変奏曲です。
この変奏曲も≪『見よ勇者は帰る』の主題による12の変奏曲≫と同じく、演奏旅行先の国王のために作曲されたものです。
「運命」や「悲愴」と同じハ短調の変奏曲
独奏主題による32の変奏曲 ハ短調 WoO80
ベートーヴェンが1806年 に作曲したピアノ独奏のための変奏曲です。
ハ短調は、ベートーヴェンが感情のドラマや苦悩を表現する際によく用いた調性です。交響曲第5番《運命》やピアノ・ソナタ第8番《悲愴》など、ハ短調の作品には強い感情が込められています。
この変奏曲も例外ではなく、劇的で緊張感あふれる雰囲気で、ドラマチックに展開していきます。
作品番号を与えられなかった作品ながらも、演奏されることの多い作品です。
民謡をもとにした楽しい変奏曲
10の民族主題と変奏曲 Op.107
実は民謡に関する作品もたくさん手掛けているベートーヴェン。
全部で180曲近い民謡の編曲・変奏曲を手掛けています。
当時ヨーロッパでは、フランス革命やナポレオン戦争を経て、多くの国々で民族的なアイデンティティが強調されるようになっていました。この流れの中で、自国の民謡や伝統音楽が大切にされるようになったのです。
とはいえ、ベートーヴェンが自ら民謡に力を入れていたわけではなく、楽譜出版社に依頼されたもので、小遣い稼ぎのアルバイトだったと言われています。
10の民族主題と変奏曲 Op.107は、正式な作品番号が付けられた数少ない民謡作品のうちの一つ。
フルートまたはヴァイオリンとピアノのための変奏曲で、各国の民謡にユーモアと優雅さを加えた楽しい作品です。
ベートーヴェン 最後の変奏曲
ディアベリのワルツの主題による33の変奏曲 ハ長調 Op.120
通称《ディアベッリ変奏曲》。ベートーヴェンの晩年の傑作と言われている作品です。
”ディアベリ”というのは人の名前で、作曲家・出版業者であるアントン・ディアベリからとられています。
ディアベリは、自分の作曲したシンプルなワルツの主題を、当時の有名な作曲家50人に変奏してもらい出版する、という大掛かりなプロジェクトを企画しました。
そのうちの1人として依頼されたものの、共同制作には全く興味のないベートーヴェン。33変奏の、演奏時間が50分以上にも及ぶ大作に仕上げてしまいます。
結局、ベートーヴェンの変奏曲は、共同制作ではなく単独のものとして出版されたのでした。
交響曲第9番と同時期に書かれたこの作品は、華やかな変奏だけでなく、フーガ、アンダンテ、劇的な場面、ユーモアあふれる瞬間まで、まるで音楽の万華鏡のように展開していきます。
ベートーヴェンの変奏技法の集大成として、一度は聴いておきたい名作です。
まとめ
変奏曲と聞くと、同じメロディが何度も繰り返されるだけ…と思われがちですが、ベートーヴェンの手にかかればまったくの別物。ひとつの主題から信じられないほど豊かな音楽世界を生み出し、まるで小さな宇宙のように広がっていきます。
今回ご紹介した変奏曲の数々は、どれも彼の創造力とユーモア、そして深い感情が詰まった名作ばかり。ベートーヴェン=交響曲やソナタ、というイメージを持っていた方も、ぜひこの機会に“変奏曲のベートーヴェン”にも触れてみてください。聴けば聴くほど、新たな魅力が見えてくるはずです!